佐和山
長野県高森町民児協との交換民児協報告
2025年10月21日 / 令和7年度
◇日 時:令和7年10月5日(日曜日)午前10時00分 ~11時30分
◇場 所:佐和山小学校コンベンションホール及び体育館
◇参加者:長野県高森町民生児童委員17名・担当職員1名、佐和山民生委員児童委員12名
◇内 容:
【目的等】
長野県高森町民児協と佐和山民児協との交換民児協を開催いたしました。この取り組みは、他地区の民生委員・児童委員と情報交換を行い、活動への理解を深めることを目的に行われているものです。
民生委員児童委員という共通の使命を持つ者同士、地域福祉活動への熱い思いを分かち合う、実り多い一日となりました。
【佐和山民児協からのご紹介】
交流会では、佐和山学区の地域特性や、子どもから高齢者までを対象とした見守り・交流活動についてご紹介しました。
佐和山学区は、多様な顔を持つ地域です。それぞれの地域特性に応じた、きめ細やかな活動に取り組んでいる様子をお伝えしました。また、独自の取り組みとして「1 歳おめでとう訪問」や学区内諸団体が連携し、組織の枠を超えてつながる「オール佐和山」の取り組み状況についても紹介しました。

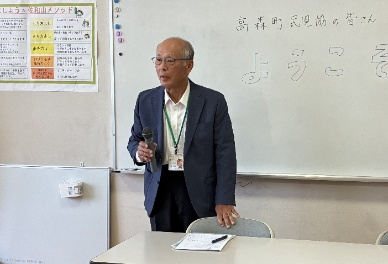
【高森町民児協の皆様からの関心と交流の様子】
高森町民児協の皆様は、佐和山学区での地域活動や活発な学区内諸団体との連携の様子に強い関心をお持ちくださり、多くの質問が寄せられるなど、活発な意見交換が繰り広げられました。
また、高森町民児協の皆様からも、日頃の地域での取り組みについて貴重な情報を共有していただきました。
乳幼児 4 か月健診での民生児童委員の取り組み
高森町では、乳幼児の4か月検診の際に、民生児童委員が直接お会いし、顔と顔を合わせる機会を設けているとのことでした。早い段階から地域と子育て家庭とのつながりを築く、たいへん素晴らしい取り組みだと感じました。
チラシ「お元気ですか」の配布
さらに、独自のチラシ「お元気ですか」を毎月作成し、一人暮らしの高齢者世帯などに配布されているそうです。地域の元気な様子を伝え、見守りにもつながる温かい広報活動に、私たちも学ぶべき点が多くありました。
【各部会での深い交流】
交流会は「児童福祉部会」「高齢者福祉部会」「心身障害者福祉部会(障害者福祉部会)」「総務部会(広報部会)」の 4つの部会に分かれて行われました。
高森町民児協の皆様からは、それぞれの地域での活動における喜びや苦労、そして地域特性に応じた課題解決への熱意が伝わってきました。総務部会(広報部会)での意見交換では、「わたしの暮らし安心安全カード」の紹介や、広報活動の工夫、協議会運営の方法、そして共通の課題である委員の担い手不足などについて、特に深く意見を交わしました。高森町の皆様は熱心に耳を傾けてくださり、大変有意義な時間となりました。


【地域一体型の子育て支援を体験:佐和山子育てひろば見学】
意見交換後には、私たち佐和山民児協が佐和山社協と共同で運営している「子育てひろば」を、高森町民児協の皆様にも見学していただきました。ここでは、地域の子どもたちが安心して遊べる場を提供しており、地域全体で子どもたちを温かく見守る取り組みを、皆様も熱心にご覧になっていました。
【交流を終えて】
今回の交流会は、日頃の活動で感じている喜びや苦労を分かち合い、民生委員児童委員の仲間として地域活動の幅を広げるヒントを得ることができる、貴重な機会となりました。
高森町民児協の皆様が、私たち佐和山民児協の取り組みから何か一つでも持ち帰り、今後の活動に生かしていただけたなら幸いです。私たち佐和山民児協も、高森町の皆様の熱心な活動姿勢から多くの刺激を受けました。この度の交流が、両協議会の今後の発展に繋がることを心より願っております。
佐和山民児協人権部会主催による「子どもの人権」研修報告
2025年10月21日 / 令和7年度
◇日 時:令和7年10月14日(火)18時~18時50分
◇場 所:佐和山小学校コンベンションホール
◇参加者:民生委員児童委員21名
◇講 師:人権啓発指導専門員
◇内 容:
彦根市人権政策課の人権啓発指導専門員(元小学校校長)を講師に招き、「子どもの人権」をテーマとした研修が実施されました。子どもを取り巻く人権課題について理解を深め、地域での支援のあり方を考える貴重な機会となりました。
研修冒頭では、人権について考えるきっかけとして、「子ども読書の日」や「民生委員の日」、子どもの権利条約採択日である11月20日の「世界子どもの日」といった記念日が紹介されました。続いて、参加者への人権に関する問いかけや、無意識の偏見(アンコンシャス・バイアス)についての説明が行われました。
1.人権とは
人権の捉え方は、「自分には関係ない」「自分を守ってくれるもの」「空気のように大切なもの」など人それぞれですが、「幸せになりたい」という思いは共通していると説明されました人権とは、本来、基本的かつ固有の権利であり、絶対的に尊重されるべきものであると強調されました。
しかし、私たちは無意識のうちに他人を傷つけてしまうことがあります。人権に関する知識不足、コミュニケーション不足、そしてアンコンシャス・バイアス」(無意識の思い込みや偏見)が、人権問題を引き起こす要因となりうることが指摘されました。

2.子どもの人権について
子どもの人権問題としては、虐待、体罰、いじめ、インターネット被害などが挙げられます。特にいじめは根絶が難しいものの、早期発見・早期解決が重要であるとされました。現代の家庭環境の変化により、家庭だけでは対応しきれない子育ての課題が増加しており、地域全体での支援が求められています。

アンコンシャス・バイアスは、性別(「保健室の先生は女性」「手芸は女性が行うもの」といった決めつけ)、年齢(「高齢者は頭が硬い」など)、国籍(「外国人は日本語がわからない」など)といった、多岐にわたる場面で生じると説明がありました。講師は、手芸サークルに男性が参加している例を挙げ、決めつけをなくすことで自身の可能性も広がると解説しました。
また、女性、高齢者、障害者、外国人、そして性的マイノリティ(LGBTQ+など)の人権についても触れられました。特に性的マイノリティについては、職場で性的アイデンティティをカミングアウトした同僚への対応事例を交えながら、理解と受け入れの重要性が強調されました。トイレや更衣室の問題など、具体的な課題を乗り越えるためには、当事者の声に耳を傾け、研修などを通じて全員の理解を深めることが不可欠であるとされました。性的マイノリティは病気ではなく、その人の生まれ持った特性であることを理解し、尊重することが求められます。
3.子どもの権利条約について
子どもの権利条約は、国内法より上位に位置する国際的な取り決めであり、日本を含む世界のほとんどの国が批准しています。この条約は、子どもを「権利の主体」と位置づけるものであると説明されました。子どもは大人に守られるだけの存在ではなく、無条件に人権を持つ一人の人間として尊重されるべき存在と規定されています。
条約の原則には、差別されないこと、子どもの最善の利益を優先すること、生命が守られること、そして子どもの意見が尊重されることが含まれます。講師は、子どもの気持ちをしっかりと聞き、尊重することが非常に大切であると強調しました。
4.子どもの基本法について
子どもの権利条約の理念に基づき、日本で制定されたのが子ども基本法です。従来の児童福祉法が「支援やサービス」の提供に重きを置いていたのに対し、子ども基本法は国や地方自治体、親が子どもに対して負う「責任」を明確にし、子どもを取り巻く問題を包括的に捉えて取り組むことを目的としていることが説明されました。
この法律が制定された背景には、いじめの重大事態の増加、不登校児童生徒の増加、10代の死因の第1位が自殺であること、子どもの相対的貧困、児童虐待件数の増加、そして子どもの自己肯定感の低さといった深刻な社会課題があることが挙げられました。
講師は、子どもの自己肯定感を高めるためには、「ダメ」という否定的な言葉を多用せず、「ありがとう」という感謝の言葉を積極的に伝えることが重要であると説きました。普段当たり前と思っていることに対しても感謝を伝えることで、子どもは「自分は役に立っている」と感じ、自尊感情を育むことができます。
また、「普通はこうするべき」「こうあるべき」といった無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)に注意し、コミュニケーションを通じて多様性を認め、尊重することの重要性が繰り返し強調されました。

5.研修のまとめと参加者の感想
研修のまとめとして、回数や時間にこだわるのではなく、参加者自身の意識変容のきっかけとなることに意義があるとし、年齢や世代を超えて思いやりを持って人と接することの大切さが強調されました。
参加者からは、「人権教育が細部(木)にこだわりすぎて全体(森)を見失っているのではないか」「『思い通りにならないと人権が侵害されている』という捉え方には疑問がある」といった意見や、「インドでは児童労働が依然として深刻であり、消費者はその現実を知るべきだ」という指摘がありました。
また、今後施行される「LGBTI 理解増進法」に基づく子どもへの教育について、幼少期や思春期の子どもへの性に関する教育は非常にデリケートであり、慎重な対応が求められるとの懸念も表明されました。
最後に、人権の主張は他者の人権と重なり合う部分があり、ゼロか100 かではなく、お互いに「折り合い」をつけることが重要であるというまとめで締めくくられました。
認知症研修報告
2025年9月3日 / 令和7年度
◇日 時:令和7年8月19日(火曜日)午後6時~7時
◇場 所:佐和山小学校コンベンションホール
◇参加者:民生委員児童委員17名
◇講 師:彦根市認知症HOTサポート職員
◇内 容
8月19日、民生委員児童委員17名は、佐和山小学校コンベンションホールにて、彦根市認知症 HOTサポートセンターの職員さん2名から、「認知症についての研修」を受けました。
この研修では、認知症の基本的な知識から、実際に認知症のご本人やご家族をどのように支えていくか、そして地域全体でどのように共生社会を築いていくかについて、幅広く学ぶ機会となりました。
1. 認知症は、決して他人事ではありません
今回の研修で、認知症が誰にとっても身近な問題であることを改めて強く感じました。
「2025年問題」として、75歳以上の高齢者の5人に1人が認知症、またはその予備軍になると推計されています。これは、私たちの地域でも、これから認知症に関するご支援が必要な方が確実に増えていくことを意味します。さらに驚いたのは、認知症は高齢者だけの問題ではないということです。
18歳から64歳の若い世代にも認知症の方がいらっしゃると聞きました。全国では約3.6万人、人口10万人あたり50.9人もの方が若年性認知症と推計されています。年齢に関わらず、誰もが認知症と無縁ではないという認識を新たにしました。
2. ご本人とご家族の「気持ち」に寄り添う大切さ
研修を通して、認知症のご本人やご家族の心に寄り添うことの重要性を深く学びました。
特に心に残ったのは、認知症のご本人が発する「笑って許してほしい」という言葉でした。困っているように見えても、まずご本人の気持ちを大切にし、焦らず、温かい気持ちで見守ることの重要性を学びました。認知症の症状は、その人によって本当に様々であり、「十人十色」であることを再認識しました。時には、認知症ではないのに、そう見える方もいらっしゃいます。私たちは、まず相手の状況にじっくり耳を傾け、安易に「認知症だ」と決めつけず、丁寧に接することの大切さを学びました。
介護をされているご家族も、様々な立場や状況で大変な思いをされています。ご家族が一人で悩まず、孤立することがないよう、必要な支援へつなぐお手伝いをしていきたいと強く思いました。
3. 地域全体で、あたたかく支え合う社会へ
認知症になっても、住み慣れた地域で自分らしく尊厳を持って暮らし続けられるよう、地域全体で支え合うことの重要性を深く学びました。
「認知症と診断されて、これからどうしたら良いのだろう」というご本人やご家族の不安な気持ちに寄り添い、適切にお医者さんや地域の相談窓口(地域包括支援センターなど)とつながることが大切です。

また、地域のサロンやカフェなど、気軽に立ち寄れる場所が、認知症の方やご家族にとって大きな心の 支えとなることも再確認しました。
特に印象的だったのは、「何でも手伝ってしまうのが、必ずしも良いわけではない」というお話です。
ご本人が「できること」を大切にし、それを応援することが、その人らしい自立した生活につながるという視点は、今後の活動において大切にしていきたいと感じました。
最後に
今回の研修を通して、認知症は決して特別な病気ではなく、誰もがなりうる可能性があり、私たち自身 もいつか関わることになるかもしれないという現実を改めて認識しました。
滋賀県立盲学校 訪問研修
2025年9月3日 / 令和7年度
◇日 時:令和7年8月18日(月)9時~11時
◇場 所:彦根市西今町 県立盲学校
◇参加者:11名
学 校 清水校長先生、辻教頭先生、伊吹先生
◇研修内容
県立盲学校について(辻教頭先生)
━要旨━
明治41年(1908年)に私塾として山本清一郎氏によって尾末町の図書館横に創立され、その後県立校として移転をしながら現在の校舎で116年目となる。卒業生は延べ1,100人を超えている。県内唯一の視覚障害教育を行っている。幼稚部から職業教育課程まで、6学部あり現在20名の方が学んでいる。(最高齢66歳)
敷地内には通学が困難な児童・生徒のために寄宿舎が併設され、7名の方が指導員と一緒に年代の違う方とも協力しながら有意義な生活を送られている。
部活動にも熱心で季節ごとに色々な競技に取り組んでおられる。

━校内見学━
校舎内の通路には物を置かない。交差する場所には点字ブロック(警戒停止は丸点、進行問題なしは長棒のブロック)で表示されている。
広い施設内で一番驚いたのは、職業教育課程の生徒が国家資格を取得するための実習として、先生立会いの下、一般の方に施術する臨床室が設備されていたことでした。
━点字体験━
学校内見学後、伊吹先生から白杖についての説明、また道に迷うなど困っている様子を見たら、傍によって「どうしました?」「何か困ってますか?」と声をかけサポートお願いしたいとのことでした。
最後に伊吹先生指導による点字体験もさせていただきました。

━最後に━
彦根に住みながら、知らないことが多かった盲学校について、説明を受け現場を見学して、点字の実体験で、視覚障害者の自立への学びを身近に感じました。民生委員として、今後の寄り添いへの基礎理解を深めました。
盲学校の先生方本当にありがとうございました。
以上
