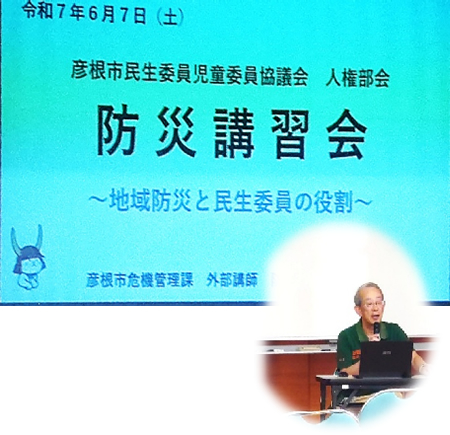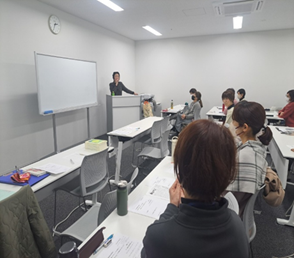障害者福祉部会 報告会および第1回研修会
2025年9月1日
◇日 時:2025年4月24日(木)10:00~12:00
◇会 場:河瀬地区公民館
◇研修内容:1)令和6年度の決算・活動報告と令和7年度の予算・活動計画を報告
2)第1回研修会
テーマ:「小中学校の特別支援学級の状況と甲良養護学校について」
講 師:県立甲良養護学校 教師 岸下 あつ子氏
◇参 加 者:35名
最初に、浅居会長・小八木副会長によるR6年度事業活動報告・決算報告、おおびR7年度事業計画案・ 予算案の説明がされ、承認された。
◇研修内容
彦根市の小中学校における特別支援学級の現状と、滋賀県立甲良養護学校について紹介と状況説明がされた。


- 1.彦根市の小中学校における特別支援学級の現状(説明者:平田民児協 原一正委員)
彦根市教育委員会の情報によると、2025年新年度における市内の特別支援学級に在籍する 児童生徒数は小学校が469名(全体の8.3%)、
中学校は171名で(同5.0%)であり近年、増加傾向にある。 - 2.県立甲良養護学校について(説明者:同校 岸下あつ子先生)
<学校概要>
●1996年4月に知的障害と肢体不自由の児童生徒を対象とした特別支援学校として開校し、本年度は創立30周年を迎えている。
校区は彦根市、多賀、甲良、豊里、愛荘の各町と東近江市の一部。
●創立前は知的障害児は八日市養護学校、肢体不自由児は八幡養護学校に通学していた。
●小学部、中学部、高等部の3学部で構成され、2025年度の在籍児童生徒数は以下の通り
小学部:75名 中学部:60名 高等部:97名 合計:232名
(障害種別内訳) 知的障害:200名 肢体不自由:32名
●居住地区別では彦根市が154名(66%)で最多
●主な通学方法はスクールバス。その他では保護者による送迎、自主通学(高等部生徒のみ)の生徒も。
(注)上記の数値は研修時の配布資料をベースに 同校ホームページより最新のものに更新している
<卒業生の進路>
●中学部の卒業生は大多数が同校高等部に進学
●高等部卒業生の進路(過去5年間の主な進路、多い順)
◆ 障害者支援施設(就労継続支援B型)
◆ 障害者支援施設(生活介護)
◆ 障害者支援施設(就労継続支援A型)
◆ 障害者支援施設(就労移行支援)
◆ 就職(一般企業の障害者雇用枠)
◆ 通所療育
◆ その他
<障害者の年金>
20歳になると「障害者基礎年金」の受給が可能
年金額は1級:103.9万円 / 年 2級:83.1万円 / 年
その他に「生活者支援給付金」の受給も可能であるが、受給要件も厳格であり基本的に生活は楽ではない。(岸下先生談)
<まとめと感想>
民生委員として心身に障害を持つ児童生徒にどのように関わり、寄り添っていくかは大変重要なテーマであるが、その難しさも多くの委員が感じていること。本人、家族の中にはプライバシーを知られたくないという感情を持つ人も少なくなく、そもそも「障害者であること自体を知ることも容易ではない」という感想が委員間の議論の場でも頻繁に出される。
甲良養護学校でも近隣地域との外部との交流もされているようなので、この研修を機会に担当地域の関連施設や行政とも話をしながら、実情を理解することを含め地道な活動をしていきたい。