障害者福祉部会第2回研修会
2024年6月7日
◇日 時: 2023年(令和5年)10月17日(火)午前10:00~11:30
◇会 場: 河瀬地区公民館
◇内 容: 「しょうがい」の捉え方と共生社会
◇講 師: 吉川 知則 氏(ステップアップ21施設長)
◇参加者: 31名/54名

2024年6月7日
◇日 時: 2023年(令和5年)10月17日(火)午前10:00~11:30
◇会 場: 河瀬地区公民館
◇内 容: 「しょうがい」の捉え方と共生社会
◇講 師: 吉川 知則 氏(ステップアップ21施設長)
◇参加者: 31名/54名

2024年5月17日
◇日 時:令和6年3月6日(水)13時30分~15時
◇会 場:彦根市福祉センター 別館2階 多目的会議室
◇研修内容:研修テーマ:「地震災害における避難行動について」 ―能登半島地震の教訓から―
◇講 師:彦根市危機管理課 防災講習会講師 消防士 笠原 恒夫 様
◇参加者 :41名

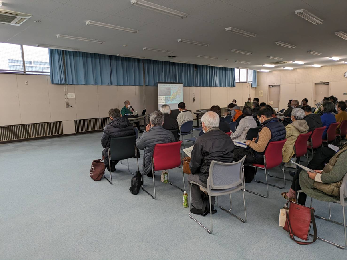
今年1月1日にM7.6、最大震度7の能登半島地震があり、甚大な被害が起こり、亡くなった方々や被災された方々にご冥福をお祈りします。 阪神淡路大震災以降、多数の大地震が起きており、日本中のどこで地震が起きてもおかしくないなかで、能登半島地震の地震が起き、 被害状況や震災後の対応状況も日々ニュースで見聞きしています。笠原様には去年から「地震災害における避難行動について」講演をお願いしていましたが、 たまたま、災害状況が容易に想像できる時期に今回の研修会を実施できたのはよかったと思います。 わたしたちがもし、地震が起きた時にどのように支援していくか考える機会になったと思います。
◇研修内容
能登半島地震は北海道から九州全土が震度1以上を示し、大きな地震であったことがわかった。 能登半島の被害状況、輪島の朝市の火災、ビルの倒壊、民家の1階部分の倒壊、がけ崩れ等の被害状況の写真を見ました。
一方、滋賀県の活断層から我々の彦根市の周りにも多くの活断層がある。琵琶湖西岸断層帯、花折断層帯、木津川断層帯、鈴鹿西縁断層帯、柳ケ瀬/関ケ原断層帯があり、 鈴鹿西縁断層帯では震度7が想定されていることが示されました。
また、地震後の避難所開設後、避難所の状況想定も時系列に従って変化し、運営の内容も変化する。学区を基本とした避難所運営委員会が立ち上がります。 その避難所運営委員会の具体的な組織の具体例が示され、役割分担の業務内容も説明がありました。民生委員は居住組として活動することになります。
災害時要支援登録者への支援方法についても具体的に準備する必要があると感じました。
(高齢者福祉部会 部会長 森 やす子)
2024年3月1日
◇日 時:令和6年2月19日(月) 10時~12時
◇会 場:プロシードアリーナ 多目的会議室
◇テーマ:各単位民児協の児童福祉部会の活動報告
◇参加者:45名
任期1年が過ぎ、各単位民児協の児童福祉部会の取り組みについて紹介してもらう企画をしました。
紹介する持ち時間も少ない中、それぞれ工夫して発表してくださいました。また地域により、学区の諸団体との連携事業や民児協主体の事業、 広報の工夫等、情報交換の場にもなり、今後の任期期間で各単位民児協の活動の参考になったと思われます。

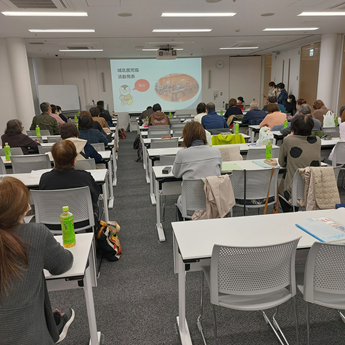

2024年3月1日
◇日 時:令和6年2月26日(火)13時30分~15時30分
◇場 所:彦根市福祉センター別館 二階多目的会議室(彦根市平田町670)
◇内 容:13:30 開会挨拶
13:35 報告事項
今年度、「ねっと彦根」発行の進捗説明 (柴田部会長)
13:50 グループ別討議
14:40 グループ別発表
15:10 全員で後片付け
15:20 終了(参加解散)
15:30 備品の後始末(役員解散)
◇参加者:34名


◇報告内容
1、広報紙「ねっと彦根」発行の進捗状況を説明。
1)「ねっと彦根」の発行日:令和6年4月1日
2)従来との違い
① 17種類から1種類へ
従来:17単位民児協の情報発信紙(17種類)として、年1回発行
今回:彦根市民児協連の情報発信紙(1種類)として、年1回発行
テーマ「子育て真っ最中のご家庭を応援する」
② 編集から完成まで
従来:各単位民児協広報部担当者が対応
今回:推進部会(プロジェクトチーム)を令和5年9月に発足。月1回推進会議開催
推進メンバー:主任児童委員部会役員4名・広報部会役員4名
③ 配布方法の変更
従来:広報部員が「ねっと彦」を引取り、地区別に配布部数を分け、所定納入場所へ搬入
今回:彦根市文書配付システムを利用し、田中印刷所に委託
2、グループ別討議


部員間の情報交換及び今後の広報活動について、テーマを決めて意見を交わした。
テーマ1: 1年を振り返って「単位民児協広報活動について」
テーマ2: 「ねっと彦根」に変わる、単位民児協広報紙の対応
テーマ3: 今後の広報活動について
テーマ4: HP(ホームページ)についてどのように思っているか
◇結びに一言
一斉改選後、一年が経過し忙しい中多くの方に出席を頂き、報告・グループ討議が出来た事は、大変有意義でありました。
「ねっと彦根」は、従来の単位民児協からの情報発信紙から、令和6年度以降は、彦根市民児協連からのテーマを絞った情報発信紙に変わりました。 今後、充実した広報紙を目指していきます。
グループ別討議は、部員間の情報交換と改善策への意見交換が積極的に行われ、今後の広報活動に繋がる有意義な時間が過ごせました。 民児協ホームページのアクセスが30,800件を超えました。HP活用(情報発信)についても、今回の意見を参考に改善を進めていきます。 今後とも、広報活動を通して、さらに多くの市民の皆様に理解と協力が得られる様、努力してまいります。
(広報部会 部会長 柴田 勝美)
2024年2月14日
令和5年度第三回目の研修会を開催しました。
◇日 時:令和6年2月3日(土曜日) 午後1時30分から午後3時まで(受付午後1時)
◇場 所:彦根市南地区公民館
◇テーマ:『地域における男女共同参画を考える』
◇講 師:彦根市男女共同参画推進委員 柴田 雅美さん
彦根市男女共同参画推進委員 沼波 洋子さん
◇参加者:46名
◇概 要
「男女共同参画」とは、男女それぞれが自らの意思によって、 人として社会のあらゆる分野において共同して、均等に活動し地域社会を構築していくもの。 今回の研修では、ピカジップ(PCAGIP)という手法を利用し、参加者をふたつのグループに分け、 それぞれのグループで、講師が進行役を務められ、相談者(1名)・板書係(2名)・質問者(他の参加者全員)を決め進行された。
それぞれの相談者は、民生委員児童委員活動や他の地域での活動を通じての悩みや相談したいと思うことを発表し、 一問一答を繰り返す形式で相談者の背景や人物像を想像しながら、決して答え(解決策)やアドバイスを言うのではなく、 相談者が問題や課題解決へのヒントを得ることができる手法です。
研修では、相談者と質問者が活発に意見を交わし、各地域のあらゆる会合や委員の活動に活用できるものと感じました。



(人権部会 部会長 馬場清司)