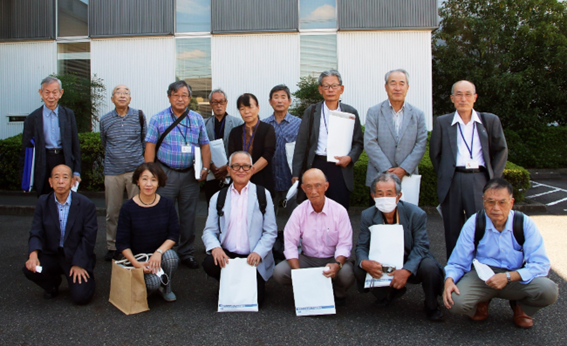◇日 時:令和5年2月6日(月) 13時30分 ~ 15時00分
◇場 所:南地区公民館
◇内 容:
13:30 開会挨拶(司会)
13:35 新役員紹介(昨年12月1日の民生委員一斉改選に伴い)
部会長 柴田 勝美(亀山学区)
副部会長 尾本 啓芳(金城学区)
平塚 聡 (城陽学区)
会計 尾本 啓芳(金城学区)
監事 臼杵 孝 (河瀬学区)
※ 広報部員人数:51名(部員名簿配布)
13:45 彦根市民生委員児童委員協議連合会のHP(ホームページ)の紹介
民生委員児童委員の活動を知って頂く為、HP閲覧の方法を説明
各単位民児協の定例会においても、HPの紹介を依頼
また、ホームページへの原稿の投稿もお願いした。
14:00 「ねっと彦根」発行編集計画の説明
広報紙「ねっと彦根」5月1日発行までの日程説明
2月6日 (月)広報部会(ねっと彦根編集計画説明)
3月2日 (木)印刷会社へ原稿の提出日
民児協ごとに印刷会社と校正する
3月24日 (金)原稿の最終校正完了日
4月1日 (土)印刷開始
4月20日 (木)印刷完成品の引き渡し日
5月1日 (月)”ねっと彦根” 発行日
14:35 情報・意見交換
14:45 終了(参加者解散)
14:45 室内除菌・備品の後始末(役員解散)
◇参加者:34名
◇結びに一言
昨年に12月1日に一斉改選が行われ、新たな3年間の任期がスタートしました。
新体制となり、今年最初の広報部会が開催されました。
広報部会開催に当たり、関係者には大変多くのアドバイスと協力を頂き、コロナ禍 感染対策をしながら無事に終了しました。
今後、
民児協活動の啓蒙と“ねっと彦根”発行に向け、広報部員一丸となって活動していきます。
(広報部会 部会長 柴田 勝美)