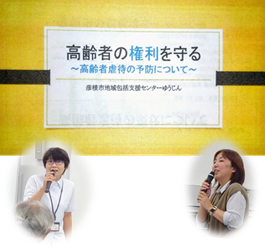令和6年度 人権部会 第2回研修会報告
2024年10月25日
令和6年度第2回目の研修会を開催しました。
◇日 時:令和6年9月28日(土曜日) 午後1時30分~午後3時30分
◇場 所:河瀬地区公民館 大会議室
◇テーマ:『子どもたちは今』
◇講 師:滋賀県教育委員会 幼少中教育課
滋賀県SSW SV 上村 文子さん
◇参加者:49名(人権部会員38名・部会員以外11名)
◇概 要
今回は『子どもたちは今』のテーマに沿って、1989年に国連で採択された「子どもの権利条約」について、 日本も批准してはいるが、まだまだそのカテゴリーによって縦割りになってしまっていること。 また、これも国連で2015年に採択されたSDGs「誰一人残さない」の理念のもと、 17のゴールのうちあえて今回は16番の「平和と公正をすべての人に」を取り上げたことを講師から説明された。 子も親も取り巻く社会問題や子育て環境の変化が激しくなり戸惑っている状態である。 「子ども基本法」で子どもの人権は、生きる権利・育つ権利・守られる権利・参加する権利の4つがあることを学んだ。 最後に、参加者に対し、①校区・地域の実情によってできることが違う ②一人の立場でできること ③チームで取り組むこと ④お互い様、共生を少しでも、というテーマで意見交換の場を設けられた。


(人権部会 部会長 馬場清司)