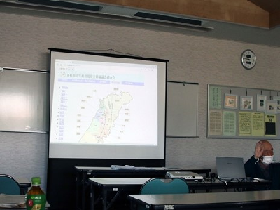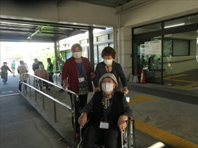「令和3年度・人権研修」
2021年7月11日
日 時 令和3年6月7日(月)13:30〜15:00
場 所 彦根市福祉センター別館2階 集団健診室
講 師 福原重和氏 彦根市人権政策課
テーマ 人に優しく 人を大切に 安全安心な職場を目指して
〜コロナ禍の人権・守秘義務・空き家問題〜
参加者 47名
コロナ禍の中、令和3年度第一回研修会を開催しました。令和2年度実績と令和3年度計画・予算報告を致しました。
向上にあると思っておりますので、研修会を重ねるたびに、 1つでも新しい情報・事例を理解して頂くことが成果だと思います。 研修会では、日常活動の中でぶつかる「守秘義務」、「コロナ禍の中だからこそ守らなければならない人権」、 「空き家問題」等々をお話しして頂きました。
1.長期にわたりコロナウイルス感染拡大から新しい言葉が出てきた。
・クラスター、ロックダウン、テレワーク・リモートワーク等々
・言葉は聞いて知っているが、意味を理解することが出来ない!
2.コロナ禍の中でどんな問題が起きているのか?
・コロナ禍の中でハラスメントが一層表面化した。
・コロナ禍で「引きこもり」「児童虐待やいじめ」「不登校」が増えた。
・体温が高め(37.5c以上)の人・マスクを着けたくても出来ない人。
・アルコール消毒が出来ない人…などが偏見の目で見られる傾向にある。
3.「民生委員・児童委員にはどのような義務があるのか?
・職務遂行の義務(民生委員法第15条)⇒守秘義務と中立公平に職務を行うことが課せられている。
4.「空き家問題について」
☆もし空き家に異常があれば建築住宅課(30-6123)までご一報ください。
☆空き家の利用及び活用については彦根市空き家バンクに連絡下さい。
研修会では知らなかった新しい言葉を数多く教えて頂き、コロナ禍における問題等々、学ぶ事の出来た研修会でした。 人権部会は、今後も研修会を重ね資質向上に努めたいと考えています。
(人権部会 部会長 梅本益夫)