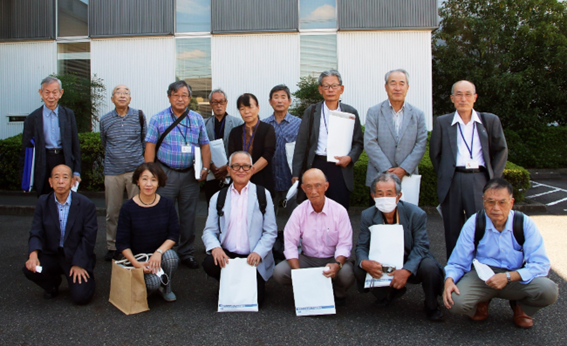◇日 時 令和4年5月18日(水)10時~12時
◇形 式 集合型
◇会 場 障害者福祉センター 多目的室
◇参加者 40名
◇報告会次第
(1)令和3年度活動実績・決算(10時00分~
(2)令和4年度活動計画・予算 ~10時40分)
◇研修会次第
(1)逃げられなかった“要支援者”(10時40分~11時10分)
NHKビデオライブラリーDVD「シリーズ東日本大震災10年」より
(2)誰もが助かる地域をめざして(11時20分~11時50分)
(3)彦根市の要支援者について (11時50分~12時)
 報告会
報告会
 第1回研修会
第1回研修会
【報告会】
冒頭、年度交代となる代表委員(4名)の紹介
旭森民児協 杉本 博様、鳥居本民児協 北川 世司夫様
稲枝民児協 篁 大英様、城西2民児協 日比 忠雄様
最初に令和3年度の活動実績と決算報告を行い、 次に令和4年度の活動計画と予算の報告をさせていただきました。
障害者福祉部会の活動も3年目を迎え、今年度は4月~11月の8ヶ月が活動期間となります。先日の役員会で、この3年間はコロナ感染問題があ
り、施設訪問研修会は松原の県立視覚障害者センター1回のみなので、「コロナ感染が終息に向かい、可能なら施設訪問研修も開催したいです
ね」とのお話しがあったことから、草津にある滋賀県立障害者福祉センターでの研修を令和4年度の活動計画と予算に入れさせていただきまし
た。
【研修会】
(1)逃げられなかった“要支援者”
NHKビデオライブラリーDVD 「シリーズ東日本大震災10年」より
東日本大震災で「逃げられなかった要支援者」は全死者の56%が高齢者でした。半数以上です。
全住民の平均死亡率0.78%に対し 全障害者の平均死亡率は1.43%です。この数値だけでも障害者の死亡率の高いことが判ります。
熊本地震 (2016年) 災害関連死の約8割が70歳以上
西日本豪雨(2018年) 倉敷市真備町 死者の8割以上が要支援者
台風19号(2019年) 死者の6割以上が高齢者
被災地からのご意見は
★要支援者のリストはあるが、地域でどう使うかが不明だった
★登録はしたが避難の仕方などの話はなかった
★登録していても安否確認がなかった
支援の有り方の反省を通して、次の(2)の誰もが助かる地域めざしてのテーマになります。
(2)誰もが助かる地域をめざして
命を救った地域のお話しとして
☆防災ネットワーク(一人の要支援者に二人が支援にあたった) ことで要支援者が救われたとの報告があった。
地域の情報として下記必要性の話しが出た。参考にしていただきたい。
☆要支援者一人一人に会った避難計画を作る必要がある
☆戸別計画で作る必要がある
戸別計画の作成状況 12%ができている
38%が未作成
50%が一部作成済み
☆避難は福祉の方がするものだと思っている
☆地域の住民と障害者とで距離があった。
☆要支援者との距離を縮めようとのことだが、出来ていなかった。
(3)地域の要支援者について
☆彦根市には11,749名の障害者登録者 (全障害者手帳での数値なので実際はもっと少ない)が在住されている。
その内、要支援者の登録は2,492人(約21%)
☆障害者福祉部会としての今後の要支援者への対応の要望意見
◎一人一人の避難計画を自主防災会と自治会と民生委員とが共有 して検討をしていただきたい。
☆障害者福祉部会としての今後の要支援者への対応の要望意見
◎要支援者の登録比率を高めていくこと。
開催メモ
●障害者福祉課から令和4年度2種類の障害者福祉を解説された冊子 (障害者福祉のてびき=身体障害者手帳 イエロー表紙)と(障害者福祉の
てびき=療育手帳 ブルー表紙)と (彦根市精神保健福祉のてびき ピンク表紙)の冊子をいただき、全員に配布しました。
●株式会社トーカイ様からは2022年度福祉用具販売総合カタログを いただき、単位民児協に1冊ずつ配布しました。
(障害者福祉部会 部会長 瀧波博之)